未解決
Community Manager
•
7.2K メッセージ
2
248
2025年6月20日 01:18
[Ask The Experts] OneFS 9.11新機能 & ObjectScale特集
あれから4年!ついに帰ってきましたAsk The Experts PowerScale !
OneFS9.11 の深堀りだけではなく、PowerScaleと共にこれからの時代を支えていくであろうObjectScaleについてもExpertさん達が語ってくれます。わからないことはどんどんExpertに聞いてみましょう!
コンテンツ目次
■OneFS 9.11の新機能「Software Journal Mirroring (SJM)」
■PowerScaleのバックアップをクラウドに!SmartSync v2発進!
■お待たせしました! 新モデル登場! NEW!
■ObjectScale CommunityEdition 4.0(体験版)のインストール手順 NEW!
期間:6月23日から2週間 (質問は23日月曜から!)
エキスパート(順不同)

Amano, Kenji (amano_kenji )
Isilonに関わって20年。AI時代の今、ますます注目を集めるIsilon(PowerScale)の魅力を伝えるべく日々奔走。最近は、進化の止まらないAIと年々衰える自分の視力を比べて複雑な気持ち。しかし「プレゼンのアマケン」はまだまだ健在!Isilon関係者はもちろん、それ以外の人たちの間にもファンは多い。

Imamoto, Keiji (KZ-2011)
あっという間に会社に15年、PowerScale(Isilon)エキスパートとしては10年選手!Dell CommunityではIsilonのスター(彗星!)
今は空を飛ぶことをやめて、日々1万歩以上を目標にウォーキングで体力維持にいそしむ毎日。これもPowerScaleと共にこの先も歩んでいきたい想いに溢れるが故。

Kaihara, Jo
社歴は19年、現場対応からプランニングまで常にお客様の伴走者として駆け抜けてきた。優し気な容貌からは程遠い、仕事に対してのストイックさは誰にも負けない。以前はマラソンでもそれを発揮していたが、今はもっぱらeSportsとバンド活動にはまっている。

Matsuo, Kou(matsuk7)
あっという間の20年!それでも毎日発見があるのでこの仕事はやめられない!PowerScaleに加えてObjectScaleも担当することになったので面白さも2倍、ファイルスとオブジェクト 、二刀流の毎日だけれど週末は愛する我が子達に一直線。世界一の応援隊長!

Mori,Hiroaki ( m_h )
エキスパートの中ではまだ若者の部類(!)に入るものの、「Ask The Experts」への参加はこれで3回目。中堅として経験を積んだ彼を頼りにするのはチームメイトだけではない。
しかし子どもとのコミュニケーションのために始めた釣りでは、なかなか釣果が出せないので、全然頼りにされない・・
 Yakabe, Kenichi
Yakabe, Kenichi
Dell Technologiesとしての社歴は3年ながら、Isilonとの付き合いは18年。Isilon(PowerScale)は、“永遠の恋人”。
思い立ったが吉日!なんでも急激に興味を持ち、一転集中で一気に覚める人。「そんなこと起こるはずがない」というトラブルほど内心興味を持ってしまう!
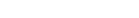

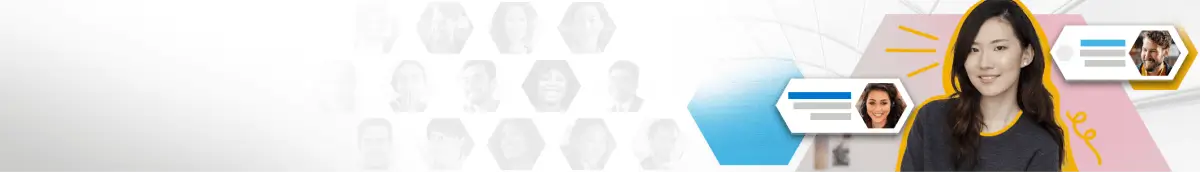
h_m
1 Rookie
•
6 メッセージ
4
2025年6月23日 00:53
OneFS 9.11の新機能「Software Journal Mirroring (SJM)」
皆様、こんにちは。今回は「Ask The Expert」OneFS 9.11新機能 & ObjectScale特集の第1回として、OneFS 9.11の新機能「Software Journal Mirroring(SJM)」についてご紹介します。
最新のOneFS 9.11以降では、PowerScale F710およびF910向けにSJMが導入されました。本記事では、SJMが登場した背景、仕組み、設定方法、そしてその他補足事項などについて解説します。
背景
近年、AIインフラストラクチャ向けストレージとしてPowerScaleをご検討いただく機会が増えています。AIの性能は「どれだけ質の高いデータを大量に扱えるか」によって大きく左右されるため、ストレージには大容量かつ高速なデータアクセス基盤が求められます。
このようなニーズを受け、PowerScale F710およびF910は、61TBおよび122TBの大容量ドライブに対応しました。
PowerScaleでは、データ保存時に各ノードのジャーナルに対してトランザクションログを書き込むことで、ファイルシステムの整合性を確保しています。ジャーナルとは「これから何を変更するか」を記録する仕組みであり、障害等でこれを失うと、処理の整合性が損なわれ、大規模な復旧作業が必要になります。
特に大容量ドライブを搭載したノードでは、万一の再構築時に復旧時間が長くなる懸念があります。そこで、F710およびF910には、ジャーナルの冗長性を高めて信頼性を強化するための機能「Software Journal Mirroring(SJM)」が実装されました。
SJMの構成と動作の仕組み
バディノード方式
同期と復旧の仕組み
自動切り替え
設定方法と確認方法
設定コマンド
isi storagepool nodepools modify <ノードプール名> --sjm-enabled true
確認コマンド
isi storagepool nodepools view <ノードプール名> | grep SJM
SJM Enabled: Yes ★有効な場合はYes
補足事項
サポート対象と前提条件
ライセンス要件
アップグレードに関する注意
まとめ
SJMは、大容量なドライブを搭載したPowerScaleノードにおいて、信頼性と可用性を確保するための重要な機能です。以下のポイントをおさえてご活用ください。
ご覧いただきありがとうございました。引き続き「Ask The Expert」OneFS 9.11新機能 & ObjectScale特集では、最新情報や技術解説をお届けしてまいります。
matsuk7
1 Rookie
•
7 メッセージ
4
2025年6月24日 23:30
[新InsightIQ6.0]
みなさま おはようございます!
いかがお過ごしでしょうか。
私は、久しぶりのAsk The Expertsでワクワクしております(^^♪
本日は、InsightIQ6.0についてご紹介させていただきます。
InsightIQは、PowerScaleの性能や保存されているファイルトレンドを確認するツールとなります。
たとえば、導入時からの容量の推移や保存したデータの種類やファイル数の確認もできます。
万が一、トラブルが発生しパフォーマンスの影響が出た際も、過去の状況と比較したりなど、
ファイルサーバーの運用には欠かせない、素晴らしい機能があります。
今回は、その最新版のInsightIQ6.0について紹介させていただきます!
まずは、ちょっと振り返りから。
InsightIQ5.Xから、Simple版とScale版があり違いは以下となります。
・Simple版は、ESX環境に展開し、目安として10クラスタ252ノードまで対応
・Scale版は、Linux環境に導入し、目安として20クラスタ504ノードまで対応
構築するベースOSと対応するノード数の規模の違いがありますが、利用機能の差はありません。
ダッシュボード画面です。下記のように性能や容量が一目で分かります。
パフォーマンス項目では下記のようにCPUなどの性能値が確認できます。(下記CPUは例です)
性能分析 CPU使用率
ファイルシステム分析では、下記のような容量推移が見えます。
容量推移 Capacity Forecast
またまた便利な機能で通知設定もあります。
運用者様視点で、下記のKPIの項目において閾値を設定し、アラート通知をすることが可能です。
例えば、使用容量が60%超えたら、Informationとしてメールでご担当者様へお知らせすることも可能です。
通知設定項目
振り返りはここまでにして。
そろそろ、InsightIQ6.0について説明させていただきます。
InsightIQ6.0のハイライト!
ポイント1 IIQ 5.xよりも軽く
ポイント2 データをさらにコンパクトに
古いデータは主にトレンドを見る目的で使われ、細かいデータを保持しておく必要性は低いため
インストール要件
現在ご利用のバージョンからinsightIQ6.0へアップグレードを検討されている方もいらっしゃると思います。
今まで、InsightIQ DBのExport/Importで対応されていたと思うのですが、現行のバージョン次第でアップグレードの方法が異なります。
下記にまとめてみました!
古いInsightIQ4.x以前のバージョンからは、InsightIQ4.4.1にアップグレードして、
そのあとOffline Data MigrationでInsightIQ6.0にするのがおすすめです。
また、注意事項もあります。
InsightIQ5.1/5.2をご利用の方は、InsightIQ6.0にアップグレードすると構成が変わりますので要注意!
InsightIQ6.0にアップグレード後、以下の構成が変わります。
注意事項
お客様ネットワーク環境によっては、IPアドレスの競合が発生する場合があり、正しくインストールができなかったり、クラスタを登録できなかったりしますので要注意!
InsightIQ 6.xには、172.17および172.18を使用する内部IPがあり、
そのIP範囲を持つクラスターの追加など、外部接続との競合が発生する可能性があります。
文書番号: 000322751に従って、修正、対処しましょう!
ここまでお付き合い頂きありがとうございました。
ぜひ、新しいInsightIQ6.0をお試しください!
(編集済)
amano.kenji
1 Rookie
•
2 メッセージ
4
2025年6月27日 15:54
PowerScaleのバックアップをクラウドに!SmartSync v2発進!
こちらご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか?
今回お伝えする内容は、v2ですよ、v2。あの小室哲哉とYOSHIKIの幻のユニットじゃないですよ(古)
というわけで(つながってない)早速今回も「Ask The Expert」行ってみよう!
OneFS9.4で「ついにクラウドにデータをコピーできる機能が実装されました。その名もSmartSync!」と大々的に発表してみたものの、その使い方は限定的、しかもワンタイムコピーのみしかできないため、人々の心を動かすどころか「そんな機能ありましたねー」と冷ややかに語られる日々・・・。SmartSyncはCloudPoolsのように細切れにして配置する構造とは違って、実データをコピー配置できる素晴らしい機能なのですが、利用シーンも限られるためコレジャナイ感使い勝手が悪かったのも事実です。
しかし、そんなSmartSyncがOneFS9.11にてVersion2となって帰ってきました。
今回発表されたSmartSync v2は、待望のインクリメンタルバックアップ機能が付きました!長らく"明日から本気出す"と言っていたSmartSyncでしたが、トミージョン手術も終えて長いリハビリ期間を経てここにきてついに本気を出してきた海の向こうの二刀流サムライの如く、こちらも本気の実装をしてきました。
今までPowerScaleのバックアップと言えば、セカンダリークラスタを導入してSyncIQで同期を取るのが常套手段でした。ところが、実際にはバックアップのお話になったときに頂戴するご意見は以下のような感じです。
「2クラスタ導入は予算的に厳しい!(でもバックアップ要件必須)」
「クラウドにバックアップしたい!(万が一のために保存しておくだけだし)」
「できれば安いクラウドストレージクラスに置きたい!(CloudPoolsは性能重視のクラスのみサポート)」
そんな願いをまるっと叶えるのがこのインクリメンタルバックアップ機能です。この機能のおかげで、ついにPowerScaleのバックアップをクラウド上のストレージに採取することができるようになりました。もちろん、従来のワンタイムコピー機能も搭載していますよ。
図1:SmartSync v2はワンタイムコピーとインクリメンタルバックアップの2つの機能を搭載
まずは対応するクラウドストレージをご紹介
はい、この一覧表を見て「おぉぉ!」って思ったそこのアナタ、いい反応です。そうなんです、注目すべきはインクリメンタルバックアップ機能のRepeat copyはGlacier IR(Instant Retreval)クラスに対応しているところなんです。これにより比較的コストを抑えたクラウドバックアップが可能になりました。
また、PowerScaleに必要なライセンスはSyncIQとSnapshotIQの2つとなります。クラウドへのデータ転送なのでCloudPoolsも必要なのでは?と思うかもしれませんが不要です。
さっそく動かしてみましょう。
動作させるためにはまずisi_dm_d本体の有効化とCAとクラウドアカウントの登録が必要ですが、
詳しい導入手順書はこちら(h19109--dell-powerscale-smartsync.pdf)を参照してください。流れはOneFS9.4から搭載されているSmartSync v1の事前準備と全く同じです。手順に沿って焦らず設定をしましょう。
図2:SmartSyncを動作させるまでの6つのステップ
さくっと事前準備を終えたら次はいよいよクラウドストレージにバックアップセットを作ります。
流れとしては、まず最初にオンプレにあるPowerScaleでDatasetを作成します。呼び名こそDatasetですが、実態はSnapshotです。このDatasetが無ければデータ転送は実行できません。
Smartsyncはこの作成されたDatasetを使ってクラウド上のバケットにデータを転送します。いわゆる「静止点を取ってバックアップを開始する」という流れですね。
図3:Datasetを作らないとデータ転送JOBは実行されない
SmartSync v2はv1同様CLIにて操作を行います。WebUIで操作できたらと私も思いますが、ここはCLIコマンドを覚えて流れるようなキータッチで華麗にバックアップジョブを操りましょう。(私もWebUI機能が欲しいんです、ほんとは・・・皆様からのご意見もお待ちしてます)
図4:Dataset(Snapshot)を作成するポリシー例。ここでは/ifs/smartのSnapshotを採取している
コツは--creation-dataset-retention-periodを指定するところです。例では86400秒(1日)の設定としていますが、スナップショットの有効期限なのでこの指定を忘れるとneverとなり、--policy-typeでEXPIRATION(削除ポリシー)を作成しても消えないDatasetが出来上がってしまいます。バックアップ用途なので必ず指定することをお勧めします。
次はいよいよバックアップジョブを実施します。
図5:長すぎるコマンド。その先にあるのはクラウドストレージへのバックアップ作成だ!と自分に言い聞かせ・・・
インクリメンタルバックアップでは特に下記を指定します。REPEAT_COPYが新たに追加されたタイプです。
--policy-type=としてREPEAT_COPYを選択
--repeat-copy-source-base-path=にはバックアップしたいディレクトリを選択
--repeat-copy-base-target-base-path=にはバケット上に作成されるバックアップセット名を記述
--repeat-copy-base-target-dataset-type=としてFILE_ON_OBJECT_BACKUPを選択
バックアップスケジュールを自動化しましょう。
SmartSyncのジョブはrecurrenceオプションを指定することでジョブを自動実行させることができます。
CREATIONポリシーでバックアップジョブで使うDataset(Snapshot)を作成させ、recurrence=“0 * * * *”といった具合に、毎時0時に動作させるよう作成します。実践的なやり方としては、Datasetを作るCREATIONジョブを動作させた直後に、REPEAT_COPYのバックアップジョブが動くように --parent-exec-policy-id=[REPEAT_COPYポリシーのID番号]を紐づけるのがおすすめです。以下の例ではジョブ4097が動作すると、その後8193のREPEAT_COPYが自動実行されます。
クラウド上に作成されたバックアップセットはどう見える?
REPEAT_COPYによって送られたバックアップデータは、クラウド上ではどのように保管されているのか。S3 Browserを使ってちょっと覗いてみましょう。
Cloud Account IDで指定したバケットの下に-repeat-copy-base-target-base-path=で指定したバックアップセットが作成され、dsid_HEADという初回フルバックアップデータ、増分バックアップのデータが作成されているのがわかります。
図6:S3 Browserを使ってバックアップセットを見たところ。各dsid番号のプロパティから増分データ量も分かる。ファイルとして見えるわけではない点は注意。
インクリメンタルバックアップモードでクラウド上に送られたディレクトリやファイルは、そのままS3 Browserなどで参照することはできません。指定されたバックアップセットをOneFSのどこかにリストアをして初めて利用することができます。
リストアをする先は、元のクラスタはもちろんですが、まったく別のクラスタにリストアを実施することも可能です。
また、#isi_dm browseコマンドを使えば、クラウド上のバックアップセットから直接特定のディレクトリやファイルを狙って戻すことも可能です。
クラウド上のデータセットは消したりリネームしたりはしないでください。あくまでもS3 Browserなどで"見るだけ"にとどめてください。
なぜ増分バックアップ方式なの?
バックアップ方式に詳しい方なら「差分バックアップ方式」と「増分バックアップ方式」の2つの差分データの保存方法があることをご存じかと思います。クラウド上のデータ保管には従量課金のためのコストが掛かってきますが、このコストを抑えられるのがSmartSync v2が採用している増分バックアップ方式なのです。加えて、HEAD情報には最新データが配置され、古いデータと入れ替えるCopy on Write方式を採用していますので、常にHEADフルバックアップは最新世代のデータセットとなります。素早く戻せる点も見逃せません。
図7:送られてきた増分データはCopy on Writeによって旧データと入れ替えが行われるため、フルバックアップデータのHEADは常に最新のデータとなる
バックアップセットから戻すのも簡単です。
戻すときは、送信元と受信先の方向を入れ替えたCOPYポリシー(--policy-type=COPY)を作成し、--copy-dataset-id=[戻したいクラウド上のデータセット番号]を指定することで戻せます。リストアしたデータに対して書き込みや削除も実施したいのであれば、--copy-create-dataset-on-target=falseは必ず指定しましょう。Policyを作成してPullにて戻したデータセットは、タイムスタンプや属性を含めて全て元通りに復元されますから、「リストアしたらタイムスタンプが変わってしまった!」という心配もご無用なのです。
図8:isi_dm browseのconnect-datasetを使ってクラウド上のファイルを閲覧。タイムスタンプをはじめとしたさまざまなメタ情報が保持されているのがわかる
もちろん、クラスタ同士でSyncIQを使ってレプリケーションする仕組みであれば、リストアの必要もなく切り替えも簡単、OneFS自慢のフェイルオーバー・フェイルバックも速やかに実行できます。今回登場したSmartSync v2のインクリメンタルバックアップ機能で、PowerScaleのバックアップの選択肢がさらに広まったかと思います。
天野(献)
(編集済)
keny6
1 Rookie
•
1 メッセージ
3
2025年7月1日 23:03
DellのAIストレージについて
Dell Technologies インフラストラクチャーソリューションズSE統括本部 データプラットフォーム ソリューションズの矢ヶ部です。
さて、この数年生成AIブームが続いていますが、各社次々と新しい概念、製品やソリューションを発表しています。Dellも例外ではなく、新しい発表があるたびに、前に発表していたものとの違いが何なのか混乱することがあります。
今回はDellのAIストレージへのアプローチについて、Dellが発表している用語を交えながら簡単にまとめたいと思います。
まずはAIのワークフローのおさらいです。
データの収集からRAGとの連携まで、次のようになっています。
求められる性能や機能はそれぞれのステップで異なりますが、例えばGPUaaSのような構成ではあらゆる用途に耐えられるよう特にトレーニング時のIO性能に注目が集まります。
全体を通してみると、IOパフォーマンス、拡張性、セキュリティ、管理機能がそれぞれバランスよく必要です。
すべてのステップでDellがPowerScaleをお勧めしていることは、ご存じの通りです。
もちろん、その他のストレージ製品が使えないということはありません。また、各ステップを1つだけの製品でカバーする必要もありません。しかしDell PowerScaleにはIsilonと呼ばれていた時代から一貫して「Data In-Place」という概念があります。
「Data In-Place」とは、データを物理的に移動させずに、その場(既存の保存先)で利用・管理・分析することができる仕組みや特性を指します。
例えばAさんが保存したファイルをBさんが編集するように、生成AIに限らず、どんな用途でも大まかに処理の流れがあります。データ量が大きく多くなるほど、データの移動(コピー)には時間がかかりますので、できるだけファイルをPowerScaleから移動せずに処理できれば効率的というわけです。またNASコントローラーが1つしかない製品では、Aさんの処理、Bさんの処理、Cさんの処理・・・がそれぞれ連続で行われる(つまり全員が同時に仕事をする)と負荷に耐えられないかもしれませんが、PowerScaleでは複数のノードが稼働するため、スムーズな処理が可能です。
ここでは4つのポイント(図中の①から④)についてどのようなストレージが最適なのかについて考えていきたいと思います。
① データ保存
AIの観点でわかりやすいのはトレーニングデータの蓄積用ですが、トレーニングデータの元となるデータとして、普段業務で使用しているNASのデータを使うこともあります。
そこでこのステップで求められるポイントは、性能、拡張性、堅牢性、管理性、セキュリティ、接続性、コストなど、AI以外の一般的なストレージ要件と同じですね。
② Data Processing:データ活用(活用準備)
このステップでは、データを集めたり、集めたデータをトレーニング用に加工します。例えば、PowerScale内のファイルはもちろん、他のシステムのデータベースからトレーニングのためのデータを取得し、加工します。
他のシステムのデータベースからデータを取得し加工するのに強力なツールがDell Data Lakehouseです。Dell Data LakehouseはSQLを使用して他のデータベースからデータを取得します。
対象となるデータソース(データベース)が複数であっても、Dell Data Lakehouseに1つのSQLを入力するだけでデータを収集し、加工し、目的のテーブルに保存します。すべてオンメモリで処理され、結果の保存先にはオブジェクトストレージ(S3プロトコル)を使います。
ここでは、Dellのオブジェクトストレージ ObjectScaleはもちろん、PowerScaleはS3プロトコルをサポートしているためそれも利用可能です。
③ Training: IO性能
ここは最も性能を求められるステップだと思いがちですが、実は目的のモデルにより必要な性能は大きくばらつきます。
例えば、医療画像のための3D画像分割を行いたい場合、1つのトレーニングデータも大きく、トレーニングデータの総容量も多くなります。この場合、GPUが求めるReadスループットは毎秒GBを超えます。一方で、言語モデルの場合、1つのトレーニングデータは数KB、トレーニングデータの総容量も画像と比べるとかなり少なくなります。GPUが求めるReadスループットは毎秒数MB程度です。
AIストレージというとAll Flashを前提にしがちですが、企業向けのAIストレージを検討する場合は、Hybridモデルでも問題なく利用できそうです。PowerScaleの場合、All FlashモデルとHybridモデルの階層構成もサポートしていますので、コストと性能のバランスを図った構成も考えられます。
性能を担保された構成をご所望の場合は、NVIDIA Certified Storage、BasePOD/SuperPOD、Cloud Partner Program(NCP)のような認定を受けた製品を選択することができます。
Dellの場合、PowerScale F710ですべての認定を受けています。例えばNCPの場合、4SU(Scalable Unit)あたりの要求性能は、160GB/sのRead、80GB/sのWriteです。これを10ノードのPowerScale F710で満たします。
Guidance for Standard HPS aggregate storage performance
PowerScale F710 storage sizing for NCP deployments
ここで注意点があります。
PowerScaleの販売に携わる方はお気づきかもしれませんが、PowerSizer(DellのPowerScale用サイジングツール)で10ノード構成のF710の性能を見ると、80GB/sのWrite要件を満たしません (Readは満たしている)。これは、NVIDIAさんのNCP認定時のテスト内容と、Dellのテスト内容が違っていることが原因です。SuperPODやNCP認定ではNVIDIAさんのベンチマークできちんと結果を確認していますので、ご安心ください。
DellのPowerSizerはOneFSのバージョンが変わると性能が変わることがありますので、今はNCPの計測データのほうが高速でも、いずれPoweSizerの性能値のほうが上回る可能性があります。AI用途の場合はSuperPOD/NCPの性能を正としながらも、PowerSizerの情報と比較し、より新しい情報を参照するようにしましょう。
わからなくなった場合は、Dellの営業までご連絡ください。
現在、すべてのステップについてPowerScaleで対応可能ですが、DellではGPUaaSのような大規模AI基盤において、トレーニングで求められる性能が近い将来さらに高まると考えています。
そこで計画しているのがProject Lightningです。
Project Lightningは並列ファイルシステムであり、PowerScaleのようなNASではありません。クライアント側に専用のドライバソフトウェアをインストールし、クライアントからはローカルファイルシステムとして認識されます。開発途中で計測された性能では、他社の並列ファイルシステムと比較して最大2倍程度のスループットがでるともいわれています。PowerScaleとは異なるファイルシステムのため、SmartPools(PowerScale間の階層機能)は利用できませんが、PowerScaleとファイルをやり取りする仕組みも検討されています。
④ RAG連携
生成AIが外部データを検索して回答の精度を高める技術として、RAGがあります。LLM(大規模言語モデル)が知らない情報でも、データベースから検索した情報を元に回答を生成できます。RAGは情報を蓄積するためのデータベースを持っています。このデータベースを最新に保つことで正確な情報を維持できます。このデータベースを最新に保つには、定期的に他のデータベースから構造化データを読み込むことや、ファイルを読み込むことが必要です。
ファイルを読み込む場合、RAGのシステムは最新のファイルがどこにあるか(ファイルのフルPath)を知る必要があります。例えば、PowerScaleに多くの社員が日々保存した業務ファイルをRAGに読み込むことを想像してください。それぞれの社員は自分のフォルダを利用するため、コマンドを駆使して新しいファイル/更新されたファイルの一覧を作り出すことは大きな手間と時間を要します。
そこで、PowerScaleでは「MetadataIQ」という機能で、ファイルのメタデータ(ファイルの名前や、Pathやタイムスタンプなどの属性情報)を外部のデータベース(Elasticsearch)へ取り出すことにしました。一度データベースに入ると、SQLで簡単に「昨日更新/新規作成されたドキュメント」ファイルの一覧を作り出すことができます。この一覧を使いRAGが読み込むべきファイルを特定し、RAGのデータベースに反映します。日々「ファイルの更新」、「メタデータのエクスポート」、「RAGデータベースの取り込み」を繰り返すことでRAGのデータベースを最新に保つことができます。
Dellのアプローチ:AI FactoryとAI Factory with NVIDIA
Dellでは、データの収集からモデル作成・運用、ビジネス成果を得るまでの流れを工場に例えて「Dell AI Factory」と呼んでいます。そこで必要になるインフラ、サービス、エコシステム(AI関連のパートナー企業の製品)が工場の生産ラインに相当します。
これにNVIDIAさんと協力して具体的なDellとNVIDIAのインフラ製品やサービスを組み合わせたソリューションセットを「AI Factory with NVIDIA」と呼んでいます。AIワークロードに最適化された製品、ソリューション、サービスのポートフォリオで構成されたT-Shirt Sizingアプローチを取っています。ハードウェアが1台のサーバだけの構成から、GPUサーバ/ネットワークスイッチ/ストレージを含む大きな構成まで用意されていますので、お客様が実現したい内容にあわせて最適な組み合わせを選ぶことができます。全て「Validated Design」ですので構成後にトラブルになることがありません。また、ネットワークケーブルなど小物も含めて提供されます。
以上が、DellのAIストレージに対するアプローチの概要です。私たちの目標は、皆様のAIワークロードを最適化し、効率的かつ安全にデータを管理するための最適なソリューションを提供することです。Dell Technologiesは、常に最新の技術と革新的なソリューションを提供し続けることで、皆様のビジネスの成功をサポートいたします。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
KZ-2011
1 Rookie
•
123 メッセージ
4
2025年7月3日 01:16
お待たせしました! 新モデル登場!
今年の梅雨は短く、近畿/中国/九州では6月27日という統計開始の1951年以降で最も早い梅雨明けとなりました。梅雨明け目前の6月25日にPowerScale ハイブリッドモデルおよびアーカイブモデルの新モデルが発売開始されました!
その名も「H710/H7100」と「A310/A3100」。
この新モデルが太平洋高気圧をパワーアップさせて梅雨明けを早めたのではと密かに思っているのは私だけではないはず。
All Flashモデルが先行してF910/F710/F210と世代が新しくなっていましたが、ハイブリッドおよびアーカイブモデルのモデル名にも「1」が入りました。
【注意】F710とH710を見間違わないように気を付けてください。FとHでは大違いですので。。。
シンプルに、H710/7100はH700/7000の後継、A310/3100はA300/3000の後継となります。見てお分かりの通り、4Uシャーシに搭載するこれまでのアーキテクチャを継承しています。「継承と言われても過去のこと知らないし。。。」という方は、前モデル、前々モデル共に過去のAsk The Expertsで紹介していますので、是非こちらも参照ください。
前モデルを紹介したAsk The Experts(2021年12月)
前々モデルを紹介したAsk The Experts(2017年9月)
今回の新モデルは、『①CPUやメモリなどの構成パーツの刷新』と『②過去からの投資保護』がポイントとなります。
早速、ハードスペックがどのように変わったか見ていきましょう。
旧モデルのポジショニングを変えることなく新しい世代のCPU/メモリに刷新していますが、ハードディスクやネットワークインターフェースなどの仕様は変わりありません。CPUはIntel Xeon Cascade LakeからSapphire Rapidsへと2世代のジャンプアップ、メモリはDDR4からDDR5へとアップしています。大きな変革を遂げたわけではない正常進化にあたりますが、32TB HDD搭載計画といった今後の進化も楽しみなところです。
性能に関しての具体的な情報をお伝えすることはできませんが、社内ベンチマークにおいて全体的に底上げされた良好な数値となっています。中でも、A310/3100ではCPUスペックの向上により、CPUパワーが最も必要となるWriteスループットが前モデルに比べて2倍以上という情報もあります。A310/3100のカバー範囲がさらに広がった感がありますね。「もうアーカイブモデルとは言わせない」と言わんばかりの進化を遂げています。
PowerScaleは、長い期間ご利用いただくために、お客様がこれまで投資してきた資産が無駄にならないようにというDNAのもと製品が開発されています。それが「ノード互換」になります。PowerScaleには、世代が異なるモデルも同一モデルと見なすことができる機能があります。以下がノード互換の一覧になります。
2世代前のモデルと互換性があり、2世代に渡って同一ノードプールとして構成することができます。ノード数が少ないクラスタでは、同一ノードプールに追加することで容量効率が良くなりますし、「2ノードだけ増設したい」という場面でもノード互換はありがたい機能になります。とは言え、ノードプールは分かれますが、最小ノード数(4Uシャーシモデルは4ノード)さえクリアすれば異なるモデルが混在したクラスタ構成を取ることができます。その場合でもファイルシステムは一つのまま拡張できることはご存じのことと思いますが、ノード互換に強く縛られるわけではなく、その時々で最適なモデルを柔軟に増設していける点はPowerScaleの特徴の一つでもあります。
参考までに、過去に互換性がない世代交代はありましたが、技術革新を優先した方がお客様のメリットが大きいという理由から製品の刷新がなされたタイミングがありました。(まさにGen6、およびPowerEdgeベースのAll Flashモデルの登場がそれでした)
一点注意いただきたいのが、新旧モデルで互換性はありますがハードウェアは異なりますので、旧モデルが搭載されたシャーシへ新モデルを搭載することはできません。シャーシ内は同一世代の同一モデルとなるように気を付けてください。
新モデルの紹介はまだ終わりではありません!!
なんと、アクセラレータがフュージョンしたのです!?
2021年、IsilonからPowerScaleへと変貌を遂げ、そのタイミングでアクセラレータが復活。あれから4年の修行を積み重ね、アクセラレータはとうとうフュージョンの技を習得しました!!
フュージョン???
ピンときた方はドラゴンボール愛好家確定です。孫悟空とベジータが合体してゴジータになり、さらに強くなるという技です。(孫悟飯とトランクスが合体してゴテンクスもあります)
これまでのアクセラレータとして、ヘッド性能を増強するパフォーマンスアクセラレータP100、2way NDMPバックアップのためのバックアップアクセラレータB100の2モデルがありました。
このP100とB100がフュージョンして誕生したのがPA110です!
「そもそもアクセラレータって何?」という方は、2021年12月のAsk The ExpertsでP100/B100について詳しく解説されていますので、こちらを参照ください。
では、合体とはどういうことでしょうか?
1台でパフォーマンスアクセラレータにもバックアップアクセラレータにもなるということです。一台二役の方が適切な表現かもしれません。もう少し具体的に解説すると、バックアップアクセラレータの最大の肝はFC HBAを搭載している点でした。P100とB100ではわずかにスペックが異なっている部分はあれど、2つのモデルの最大の違いは2way NDMPのためにテープドライブ/テープライブラリを接続するために必要となるFC HBAを搭載しているか否かでした。そこで、「わざわざ2モデルを提供するのは非効率。パフォーマンスアクセラレータにFC HBAを搭載できればシンプルだよね。」ということで、PA110はパフォーマンスアクセラレータとしての高性能なCPU/メモリスペックを搭載しながらFC HBAをオプションとして選択できるようになりました。つまり、バックアップアクセラレータとして利用したい場合は、PA110にオプションのFC HBAを追加する形となります。
物理的には、スロット2にFC HBAを搭載することでバックアップアクセラレータとなります。パフォーマンスアクセラレータとして利用する場合は、スロット2は空きとなります。これはオーダー時にFC HBAを追加するか否かを指定することになります。
以下、詳細スペックです。P100/B100と比較できるようにしていますので参考にしてください。
ベースがPowerEdge R660となり、PA110もCPUがIntel Xeon Sapphire Rapids、メモリがDDR5へと刷新されています。CPUコア数が大幅に増えたことで、極めて強力なヘッド性能を提供できるモデルとなっています。(まさにフュージョン!?)
お気付きの方もいるかと思いますが、PA110のCPUとメモリのスペックがF910/F710と全く同じです。F910/F710はネットワークインターフェースやCPUがボトルネックになる傾向にあり、NVMe SSDドライブの負荷に余裕がある場面があります。そのような時は、PA110を追加することでネットワークインターフェースとCPU/メモリリソースが増えるので、All Flashクラスタを容易に性能向上させることができます。All Flash環境をさらにパワーアップできるなんてスゴイですね!
アクセラレータはドライブを搭載していなくアクセラレータ用のライセンスとなるので、比較的お手頃な価格でクラスタのヘッド性能を上げることができます。アイデア次第で活用できる場面は様々あるので、覚えておいて損はないモデルです。
ドラゴンボールのフュージョンは時間が来たらまた別々の二人に戻りますが、PA110はそのままでずっとハイパワーを提供し続けます!
最後に重要な点を。
H710/7100およびA310/3100、PA110は、OneFS 9.11からのサポートとなります。既存クラスタへこれら新モデルを増設する際には、予めクラスタのOneFSバージョンを9.11以降へアップグレードしてください。
ここでは紹介しきれなかったバックエンドスイッチの新モデル(Z9664FおよびArista 7308X3)や122TB SSDドライブ、F910/F710のInfinibandフロントネットワーク接続対応なども登場しており、PowerScaleは絶え間なく進化し続けています。
この先もOneFS含めて様々な進化が計画されていますので、今後もPowerScaleにご注目ください!
(編集済)
joekai
1 Rookie
•
21 メッセージ
3
2025年7月3日 08:05
ObjectScale CommunityEdition 4.0(体験版)のインストール手順
本日は、弊社オブジェクトストレージであるECSからリブランドされた、ObjectScale(OBS)の無料ova版である、ObjectScale CommunityEditionのインストール方法をご紹介します。
オブジェクトストレージとは、ファイルストレージのようなディレクトリ構造をもたず、キーで管理されたコンテンツを蓄積していくストレージです。ディレクトリ構造によくある、ディレクトリ内ファイル数等の制約がなく、ディレクトリ構造を気にせず無尽蔵にオブジェクトを追加していくことが出来ます。
プロトコルはAWS S3を使うのが最近の主流で、cloud nativeなアプリケーション環境をオンプレミスで展開したい場合に非常に有用です。Hadoop環境で用いるS3aも使用でき、その他,NFS,Swift,CASなどにも対応します。おなじみPowerscaleでもS3を使うことは出来ますが、対応するAPIや拡張性はObjectScaleの方が優れており、用途によってはObjectScaleをお勧めしています。
そんなオブジェクトストレージの体験版を、この機会に是非お試し下さい!
ダウンロード
以下のURLから、ovaファイルをダウンロード出来ます
https://130751444065420395.public.ecstestdrive.com/ecs-ce/DELL-OBSCE-4.0.0.0-OVA.ova
以下、 Githubページのトップになります。こちらの内容に従うことでもセットアップは可能です。
https://github.com/EMCECS/ECS-CommunityEdition
インストール
ダウンロードしたovaファイルを、ESXiにdeproyします。リソースは以下を推奨しております。推奨値の要求基準はちょっと高めですが、動作が安定します。
動作に必要な下限値は以下
初期設定① ネットワーク設定
デプロイ完了後、ESXiのコンソールからログインします。ユーザー/パスワードは
user:admin
password:ChangeMe
です。
まずネットワークの設定を行います。ObjectScaleの基幹OSはSuSEで作られているため、SuSEのネットワーク設定変更が行える手順なら何でも良いですが、nmtuiを使うのが一番簡単でしょう。
nmtui
Edit a connectionを選び、ネットワーク設定を行います。
設定が終わったらActivateします。
このとき、Activateが失敗したり、成功してもその後不安定な場合は、ネットワークの設定を見直してみたり、IPの競合を疑ってみたりしてください。
初期設定② videploy
初期設定用のファイルを編集します。こちらはコンソールからでも、sshアクセスでも構いません。特に何もなければsshアクセスで行います。
videploy
viモードになってエディタが開かれます。何か所か編集する必要があります。
install_node: xx.xx.xx.xx →先ほど設定したOBSCEのIPに変更
ecs_block_devices: - /dev/vda →/dev/sdb
members: xx.xx.xx.xx →先ほど設定したOBSCEのIPに変更
ecs_block_devices: - /dev/vda →/dev/sdb
必要に応じてdns_serversとntp_serversのIPも編集します
編集したテキストをsaveします。(Esc+wq!等)
保存終了後、自動的にスクリプトが流れますので、スクリプトの正常終了を確認します。
初期設定③ ova-step1
初期セットアップスクリプトその1を流します。以下のコマンドを実行してください。
ova-step1
特に問題が無ければ、数分で終了します。これ以降webアクセスが出来るようになりますが、セットアップ手順としてはあと1ステップ残っています。
初期設定④-1 ova-step2
このステップは、このOBSCEの利用目的によって分岐するのでご注意下さい。すでに構築済みのOBSクラスタとレプリケーションを組みたい場合は、このステップを実行してはいけません。初期設定④-2へ飛んで下さい。
通常のクラスタ構築を行う場合は、以下ova-step2を実行します。
ova-step2
ライセンスの有効化、storagepoolの作成、vdcの作成、namespaceの作成、bucketの作成などの基本設定が行われます。ova-step2では複数個所で待ち時間が発生します。全体で1時間以上かかることもありますので、ご了承下さい。
初期設定④-2 ライセンス有効化
コマンドラインでライセンスを有効化します。以下のコマンドを発行します。ova-step2を実行した場合は、同手順は不要です。
ecsconfig licensing -a
ova-step1が終了してから十数分以上経過していないと、コマンドを受け取るserviceが起動しておらずエラーになります。ご注意下さい。
GUIの起動
httpsでアクセスします。
https://<OBSのIP>/
user:root
password:ChangeMe
ライセンス規約への同意を求められるので、acknowledgeを押します。
パスワードの変更を求められるので新しいパスワードを決めます。
変更後ログイン画面に戻ります。
ログインすると、チェックリストに入るか、ECSの管理画面に向かうか選べます。特になければ、チェックリストに入ります。
チェックリストを表示すると、初期設定で終わっていない項目が分かります。ova-step2行っていない場合は、ほとんどの項目のチェックが外れています。ova-step2を行っている場合は、ユーザー作成以外は完了済みとなっています。ユーザー作成のみ行って、インストール&初期設定完了です。
既存クラスタとレプリケーションを組む場合は、storage poolの作成のみ完了させます。決してVDC作成まで行ってはいけません。(作成してしまうとレプリケーションクラスタとして利用できなくなります)
レプリケーションターゲットクラスタのVDCは、ソースクラスタ(既存)からリモートVDCとして作成します。その際に、ターゲットクラスタのVDC Accesskeyが必要になります。ターゲットクラスタの管理画面から取得して下さい。
ソースクラスタ側で、ターゲットクラスタのVDCをリモートVDCとして作成します。
レプリケーション関係を組んだ場合、設定の一部はソースクラスタのものが共有されます。必要に応じて他の項目も設定してください。
以上、OBS Community Editionのインストール&初期設定の流れを説明させて頂きました。オブジェクトストレージは近年そのニーズが増加しており、それに合わせてこちらの体験版も多くのお客様にご利用頂いております。是非この機会にS3プロトコルが使えるオブジェクトストレージの使い勝手をご賞味頂ければ幸いです。
またインストール後の、ECSの使い方については、弊社の過去記事で特集させて頂いております。
https://www.dell.com/community/ja/conversations/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8-wiki/ecs%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E7%AC%AC1%E5%9B%9Eelastic-cloud-storage-ecs-community-edition-vm%E7%89%88-%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B/647f7f8cf4ccf8a8dee0e5ee
その他詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、是非弊社窓口、または弊社の御社担当営業までお問合せ下さい。
https://www.dell.com/ja-jp/lp/dt/contact-us
それでは、またの機会にお目にかかれますことを願っております。
貝原 星宇
デルテクノロジーズ
ISGデータプラットフォームソリューションズ事業本部
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
1
2025年7月7日 02:01
皆さん、
[Ask The Experts]「OneFS 9.11の新機能 & ObjectScale特集」はいかがでしたか?
Expertsの皆様には、注目のHot Topicsを取り上げていただき、ますます進化するOneFSとObjectScaleの魅力をたっぷりご紹介いただきました!
どんどん試して使って、みんなで幸せになりましょう!
[Ask The Experts]「OneFS 9.11の新機能 & ObjectScale特集」をご覧いただいた皆様、そして素晴らしい情報を投稿してくださったExpertsの皆様、2週間にわたり本当にありがとうございました。
またすぐにお会いしましょう!